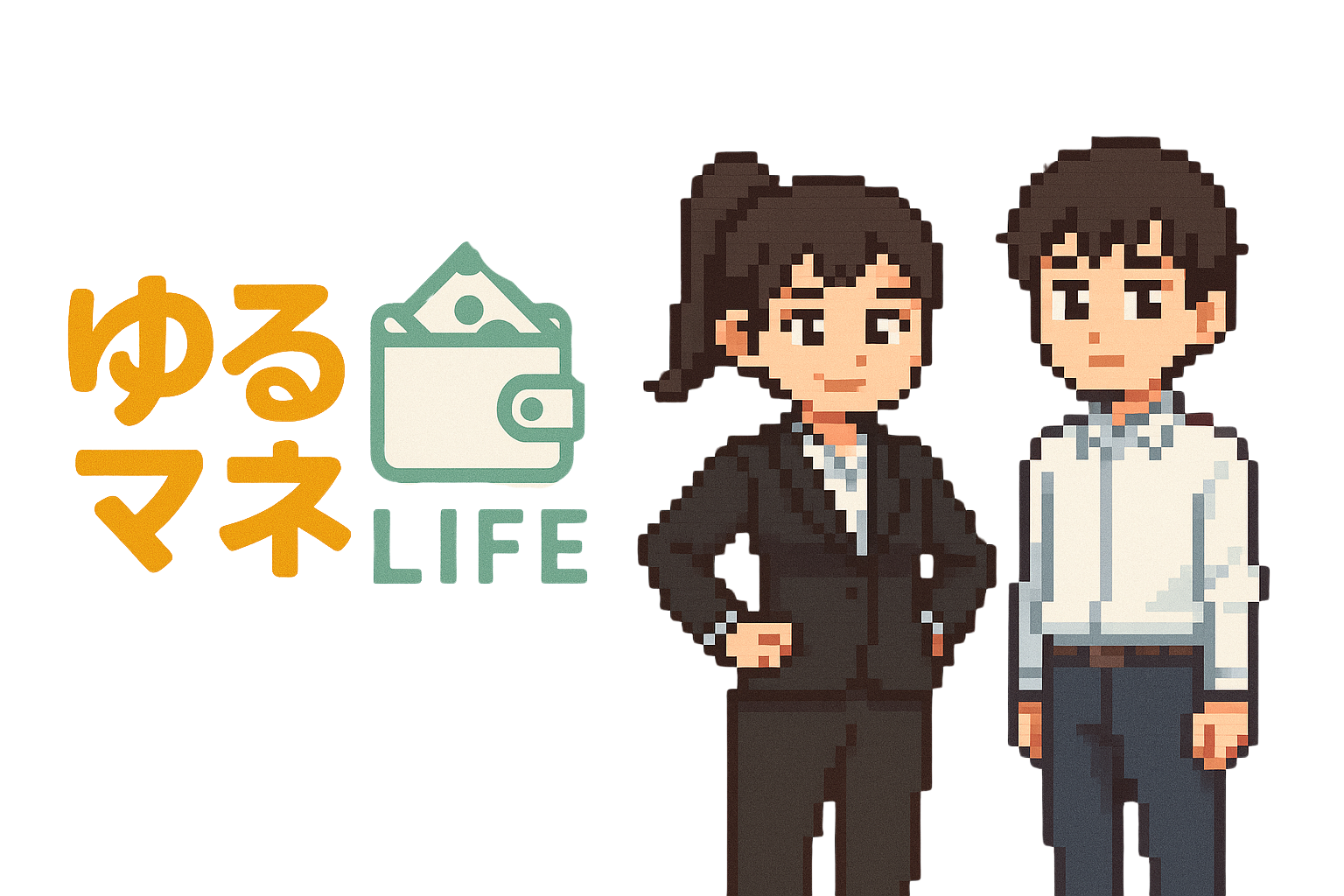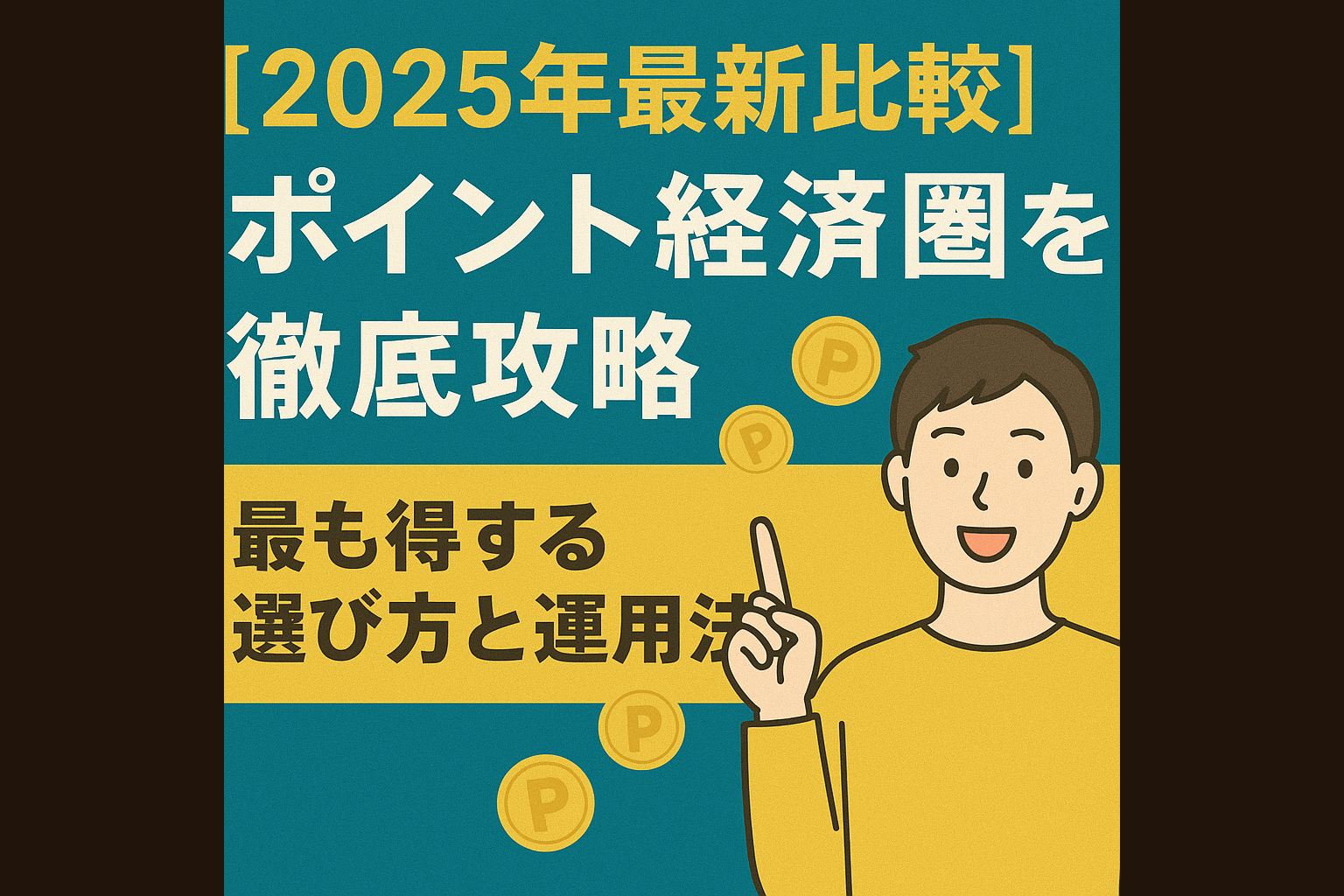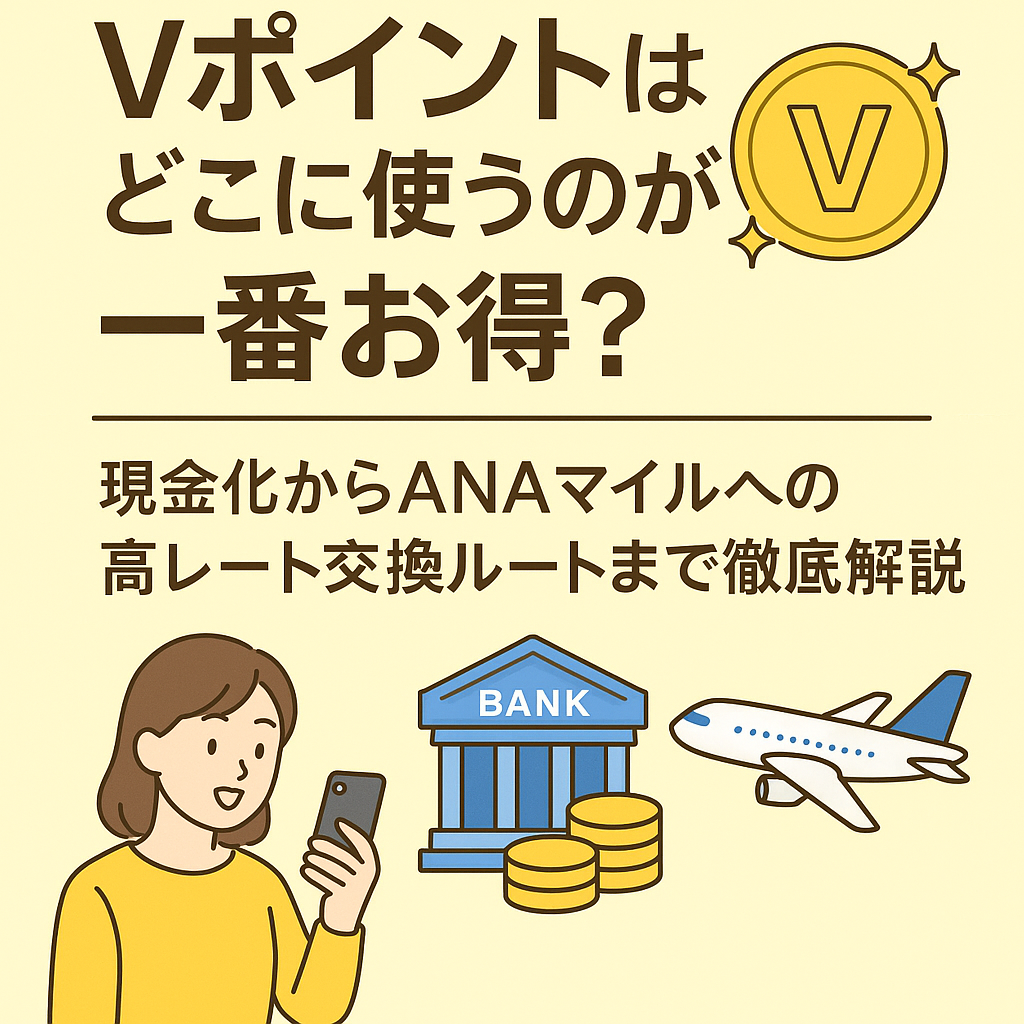景気、物価、為替…「金利」がわかる!初心者向け金融経済入門
おすすめキーワード
新着記事
News

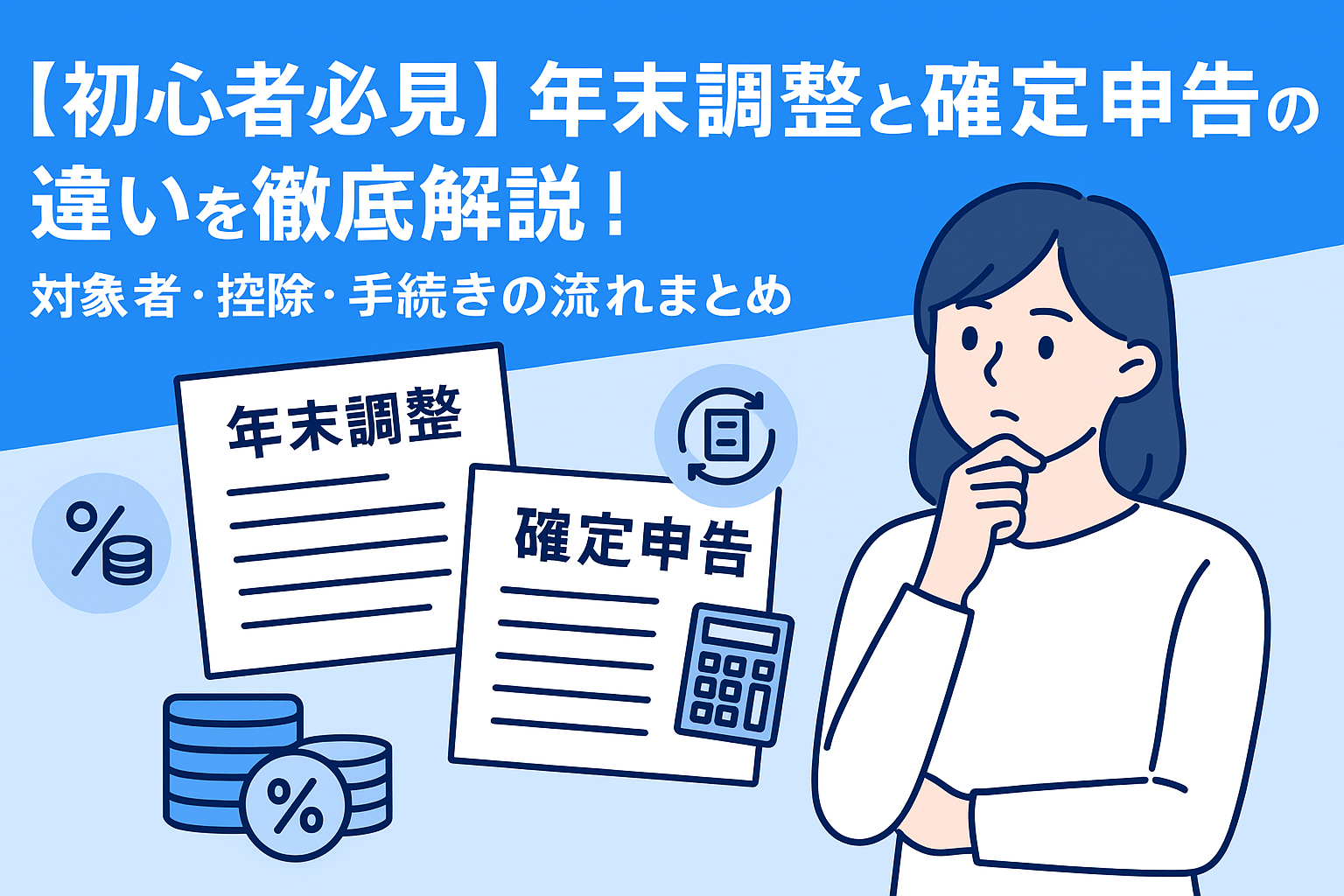
【初心者必見】年末調整と確定申告の違いを徹底解説!対象者・控除・手続きの流れまとめ
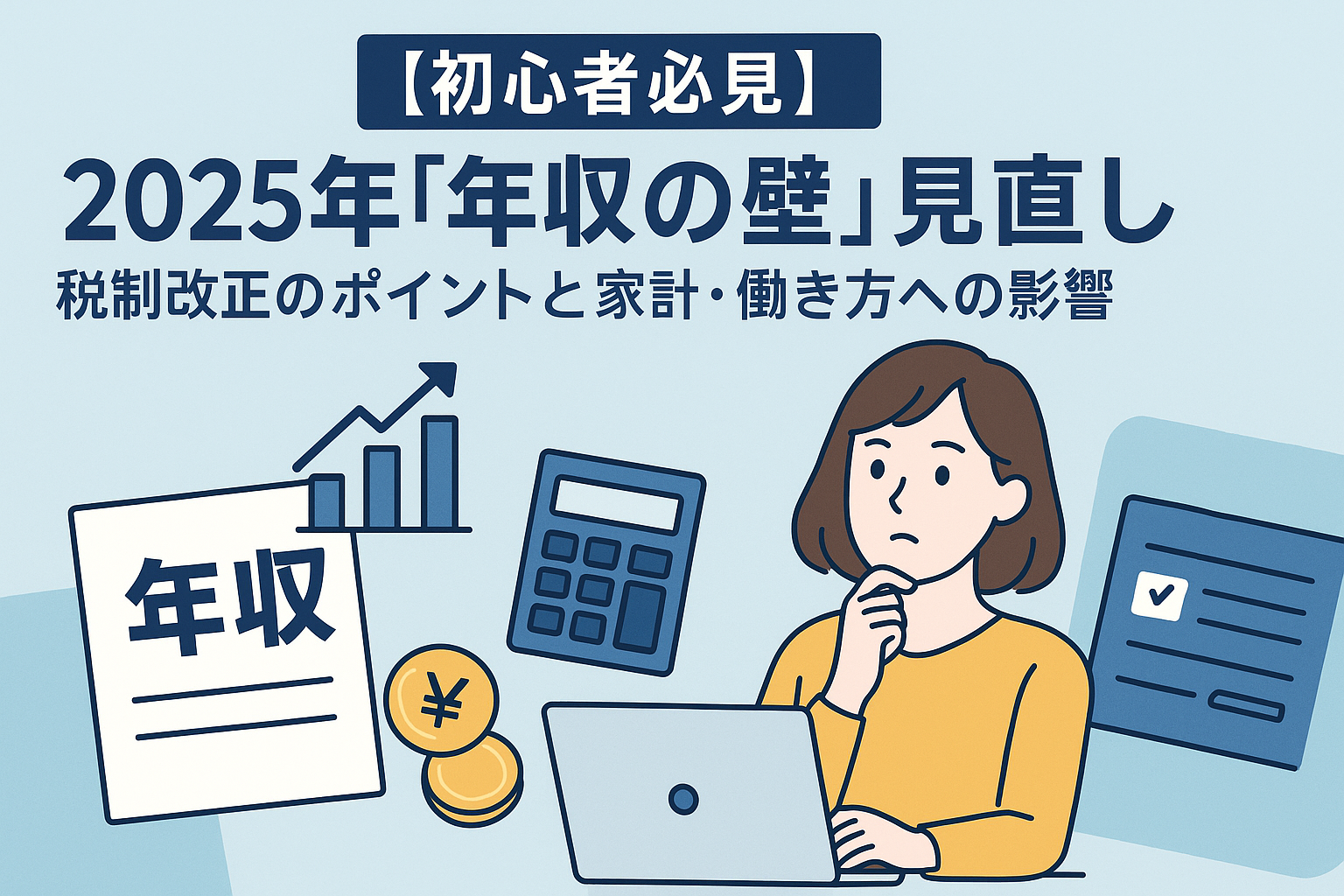
【初心者必見】2025年「年収の壁」見直し|年末調整‐税制改正のポイントと家計・働き方への影響
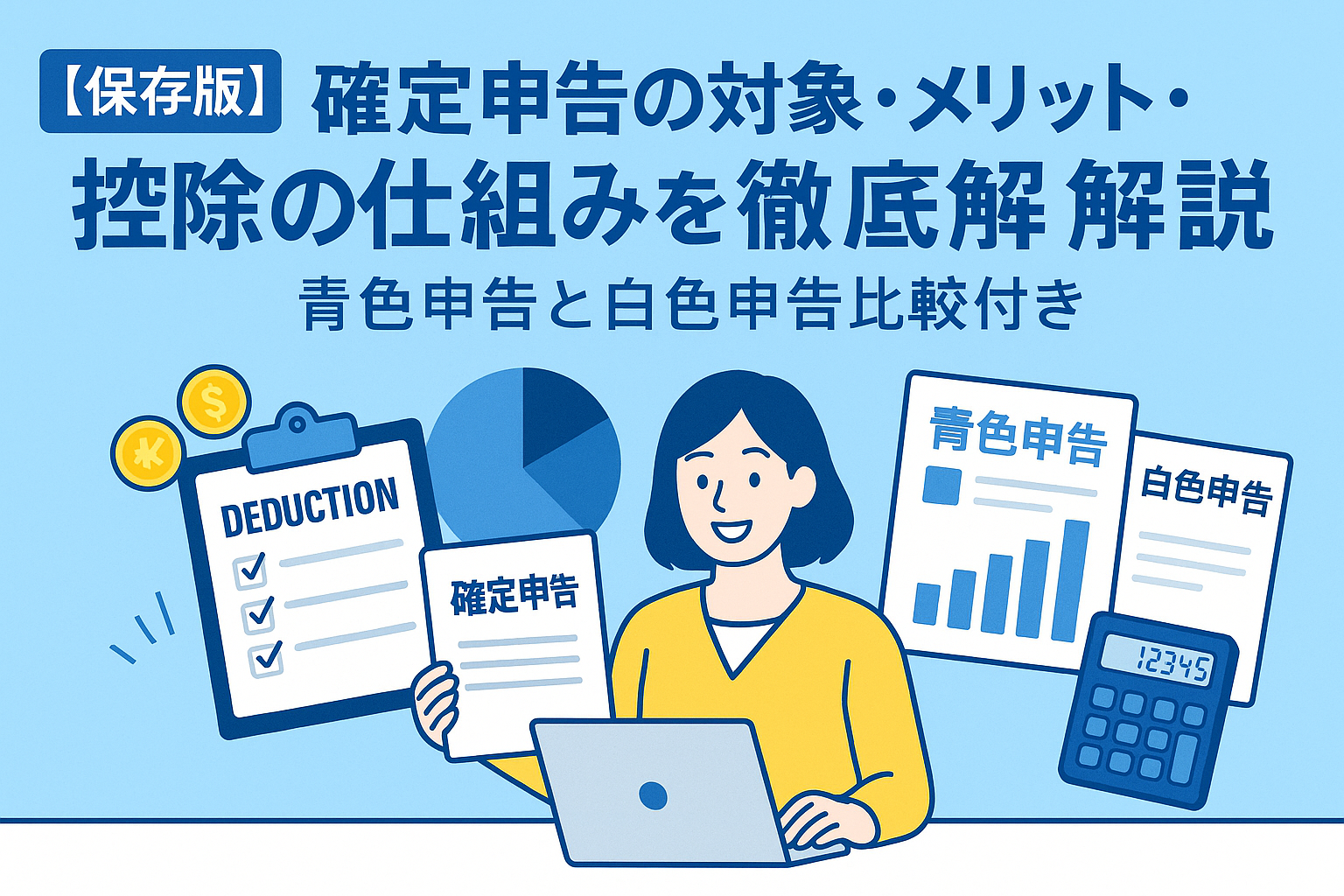
【保存版】確定申告の対象・メリット・控除の仕組みを徹底解説|青色申告と白色申告比較付き
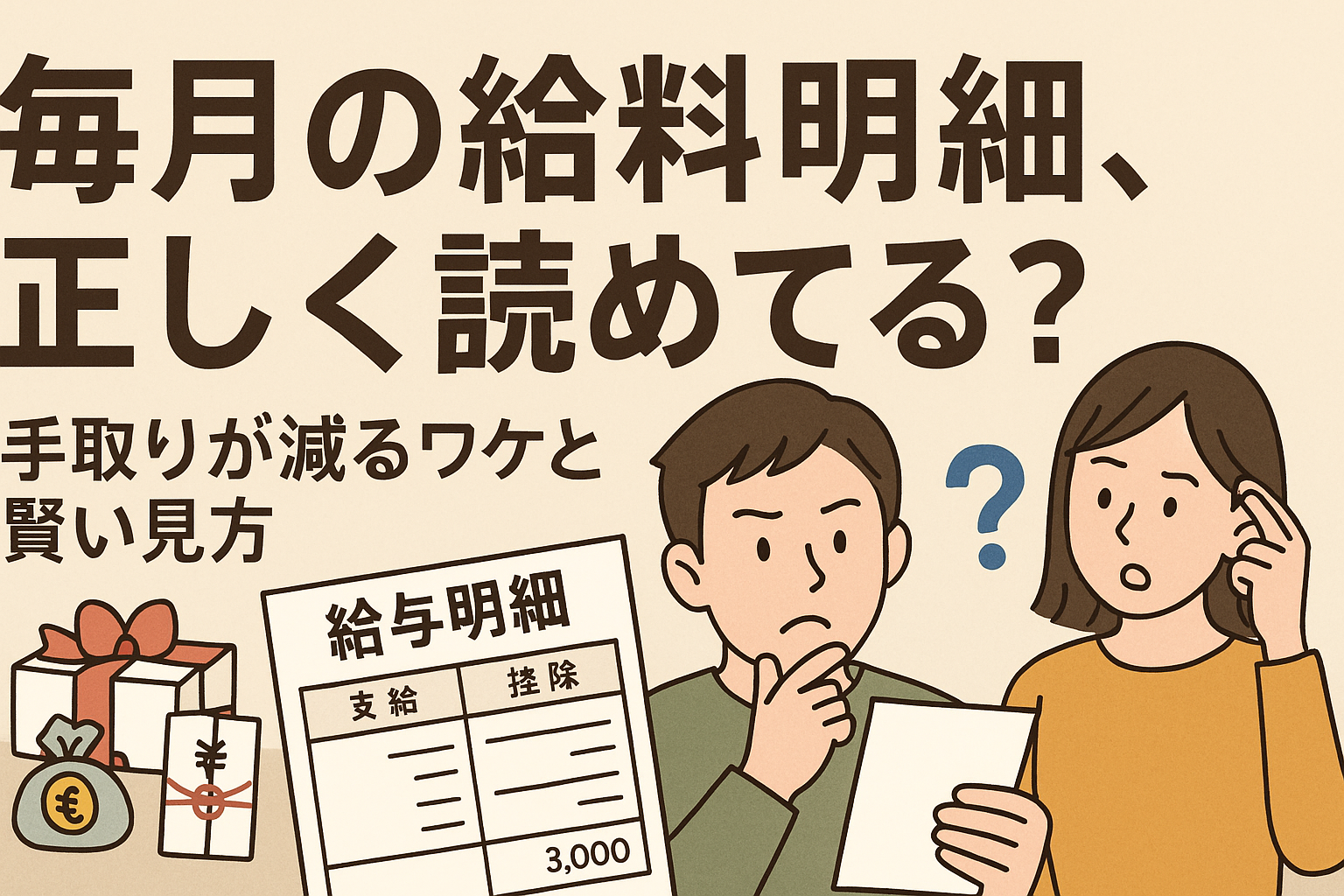
毎月の給料明細、正しく読めてる?手取りが減るワケと賢い見方

誕生日、結婚祝い、退職祝い…プレゼントの金額、どう決めてる?人間関係の親密度と予算のリアル
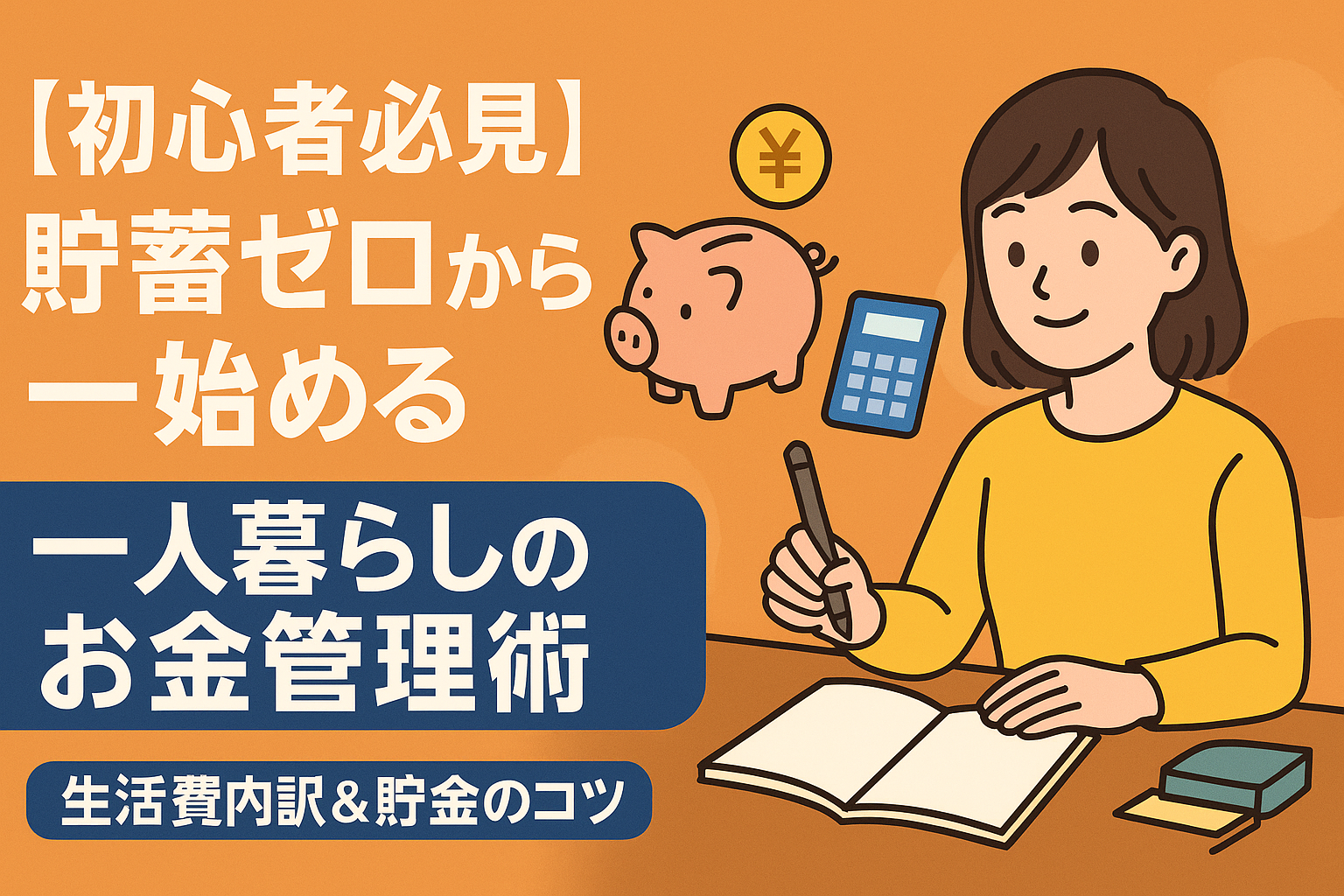
【初心者必見】貯蓄ゼロから始める一人暮らしのお金管理術|生活費内訳&貯金のコツ

【初心者向け】夫婦の金銭トラブルを防ぐ!家計管理の4パターンと実践法

【初心者必見】ライフステージ別保険の見直しポイントと損しない選び方

【知らないと損】医療費控除&高額療養費制度を徹底解説|節約の実例付き

副業収入を賢く増やす!知って得する節税テクニックと会社バレ対策
iDeCo Uncategorized Vポイント お給料 お金を使おう クレジットカード ベーシックインカム ボーナス ポイント経済圏 ポイ活 リボ払い 不動産投資 保険 初心者 副業 医療費控除 家計管理 年収 年末調整 投資 投資信託 新NISA 確定申告 税金 節約 資産形成 金利
投資
iDeCo
クレジットカード
副業
初心者向け情報
かみんぐすーん

副業収入を賢く増やす!知って得する節税テクニックと会社バレ対策

S&P500だけじゃもったいない!あなただけの最強ポートフォリオを作る「カスタマイズ戦略」

【節税しながら貯める】iDeCoと新NISA、どっちを優先すべき?あなたのタイプ別診断
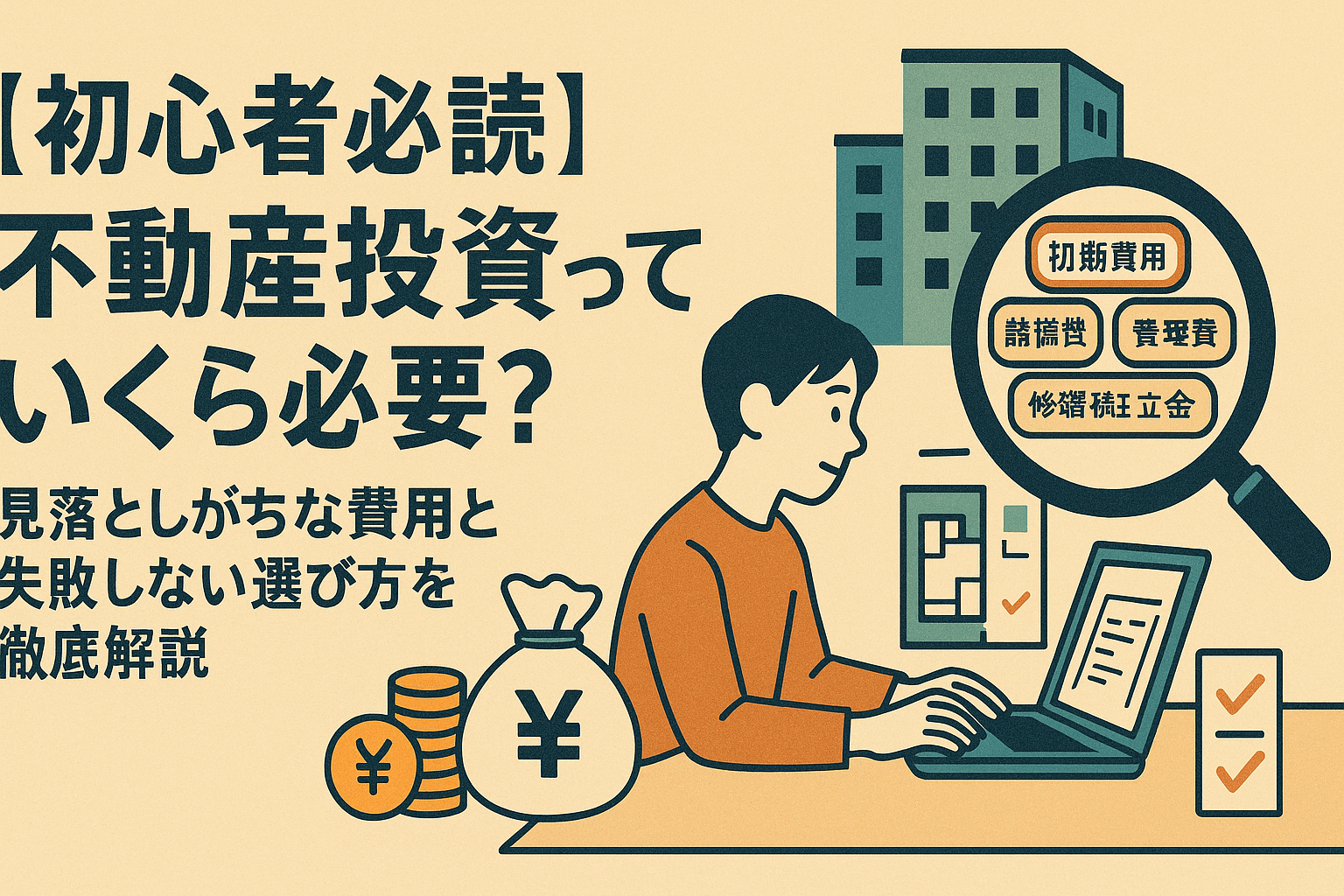
【初心者必読】不動産投資っていくら必要?見落としがちな費用と失敗しない選び方を徹底解説
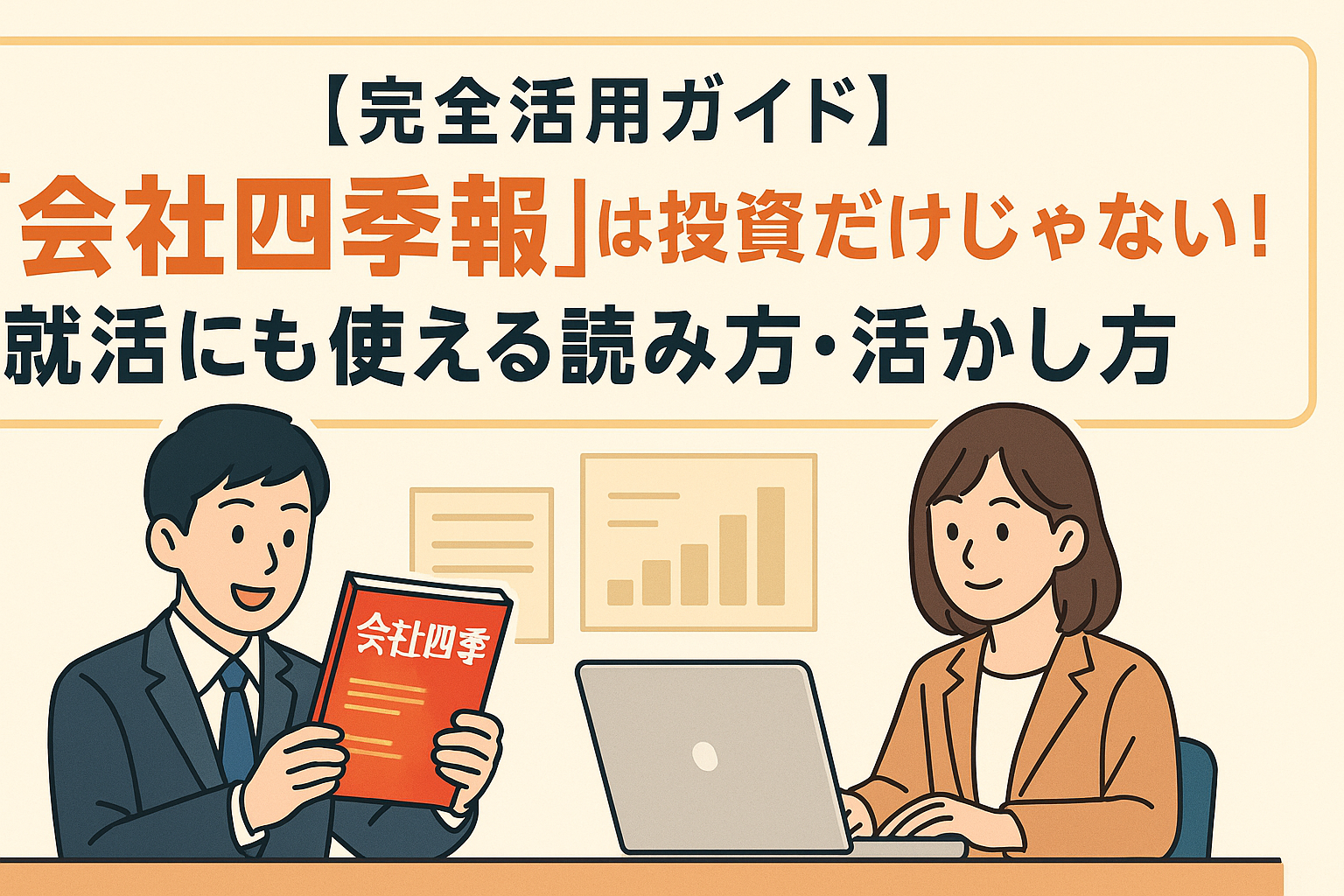
【完全活用ガイド】『会社四季報』は投資だけじゃない!就活にも使える読み方・活かし方

【今すぐ始めるべき理由】新NISAは早ければ早いほど得!20代と30代の「複利の差」をシミュレーション

【徹底解説】2025年版iDeCo制度改正|老後資金を守る賢い運用とリスク回避法

【節税しながら貯める】iDeCoと新NISA、どっちを優先すべき?あなたのタイプ別診断
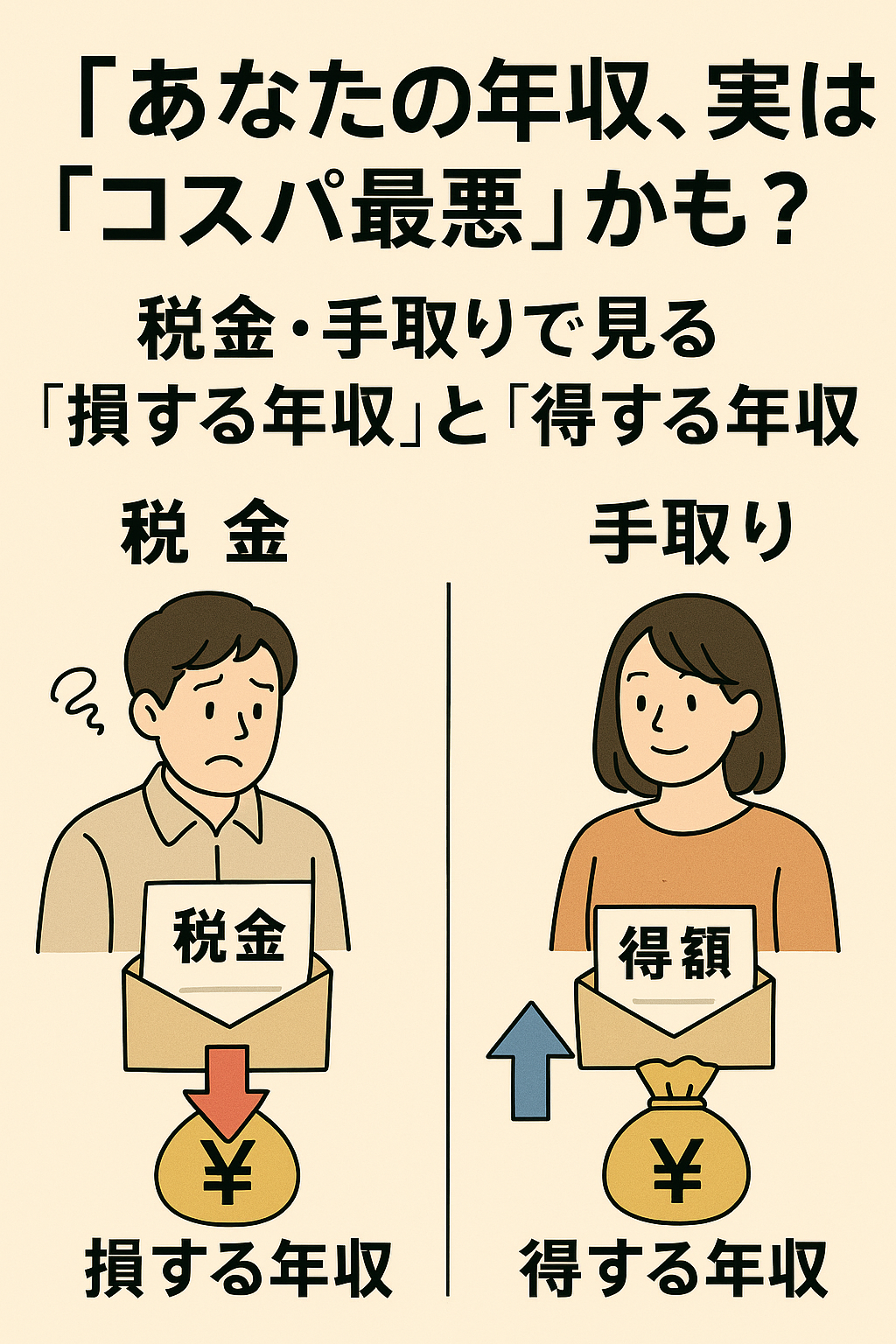
あなたの年収、実は「コスパ最悪」かも?税金・手取りで見る「損する年収」と「得する年収」

【今日から実践】毎月いくら貯金する?目標別「貯蓄額」と無理なく続ける5つのコツ
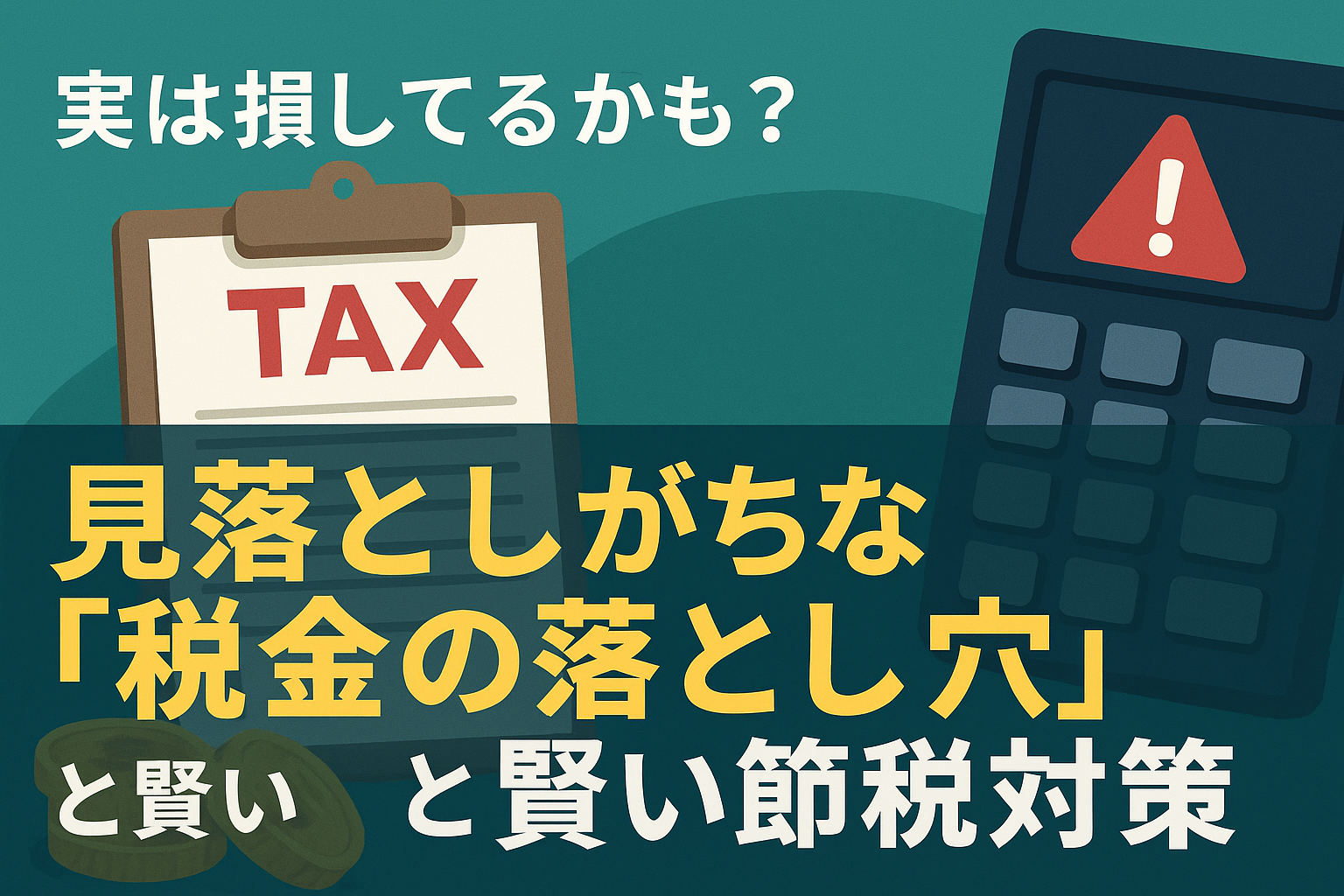
【実は損してるかも?】見落としがちな「税金の落とし穴」と賢い節税対策
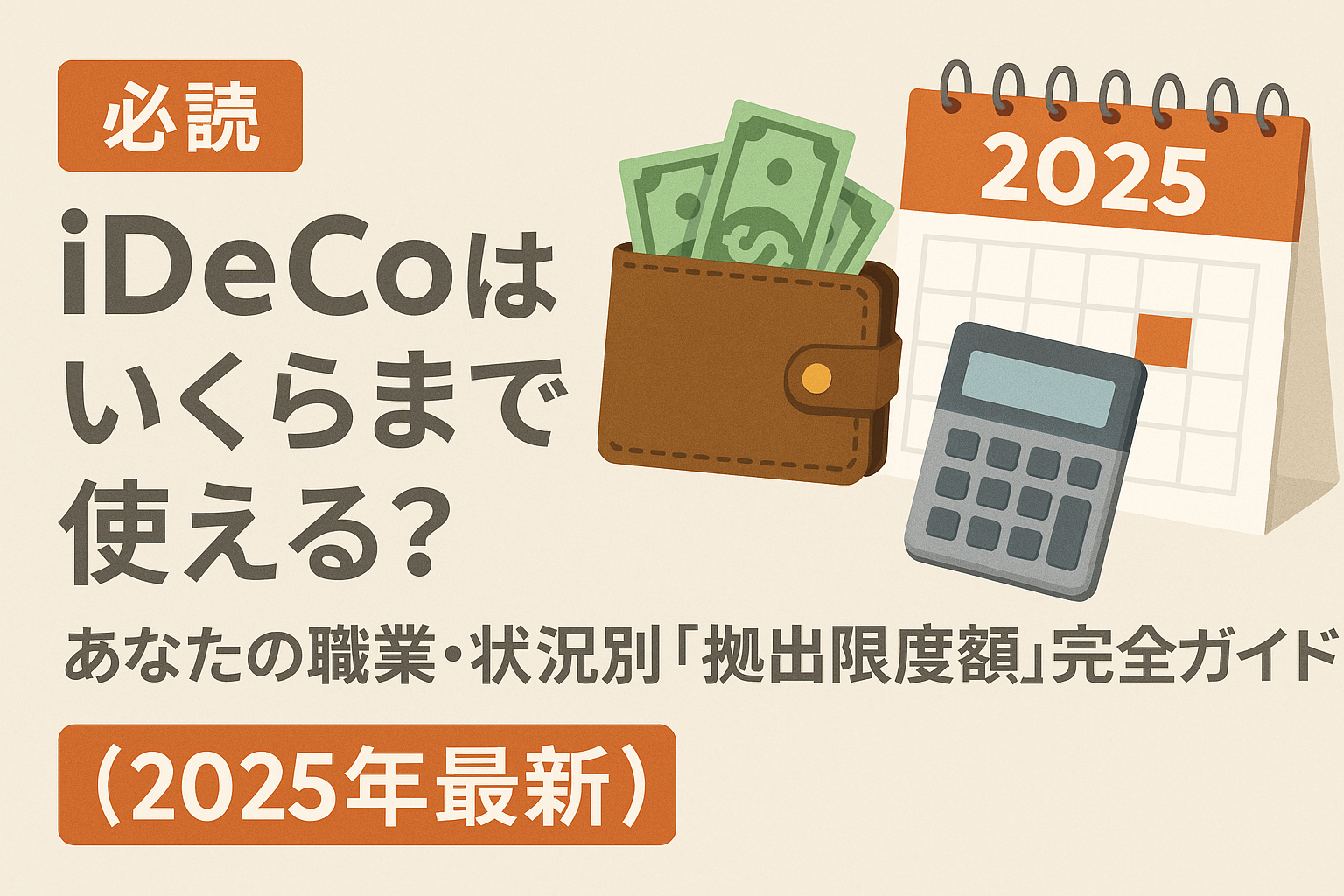
【必読】iDeCoはいくらまで使える?あなたの職業・状況別「拠出限度額」完全ガイド(2025年最新版)

【知らないと損!】「ポイ活」だけじゃない!クレカ選びの新常識:特典&サービスの意外な活用術

【知らないと損!】「ポイント還元率」だけじゃない!クレカ選びの新常識:特典&サービスの意外な活用術

【脱・キャッシュレス迷子】ポイントも使い方も最適化!スマホ決済「メイン一本化」のススメ

【脱・ポイ活疲れ】本当に「お得」なポイントはこれだけ!賢いポイント活用術
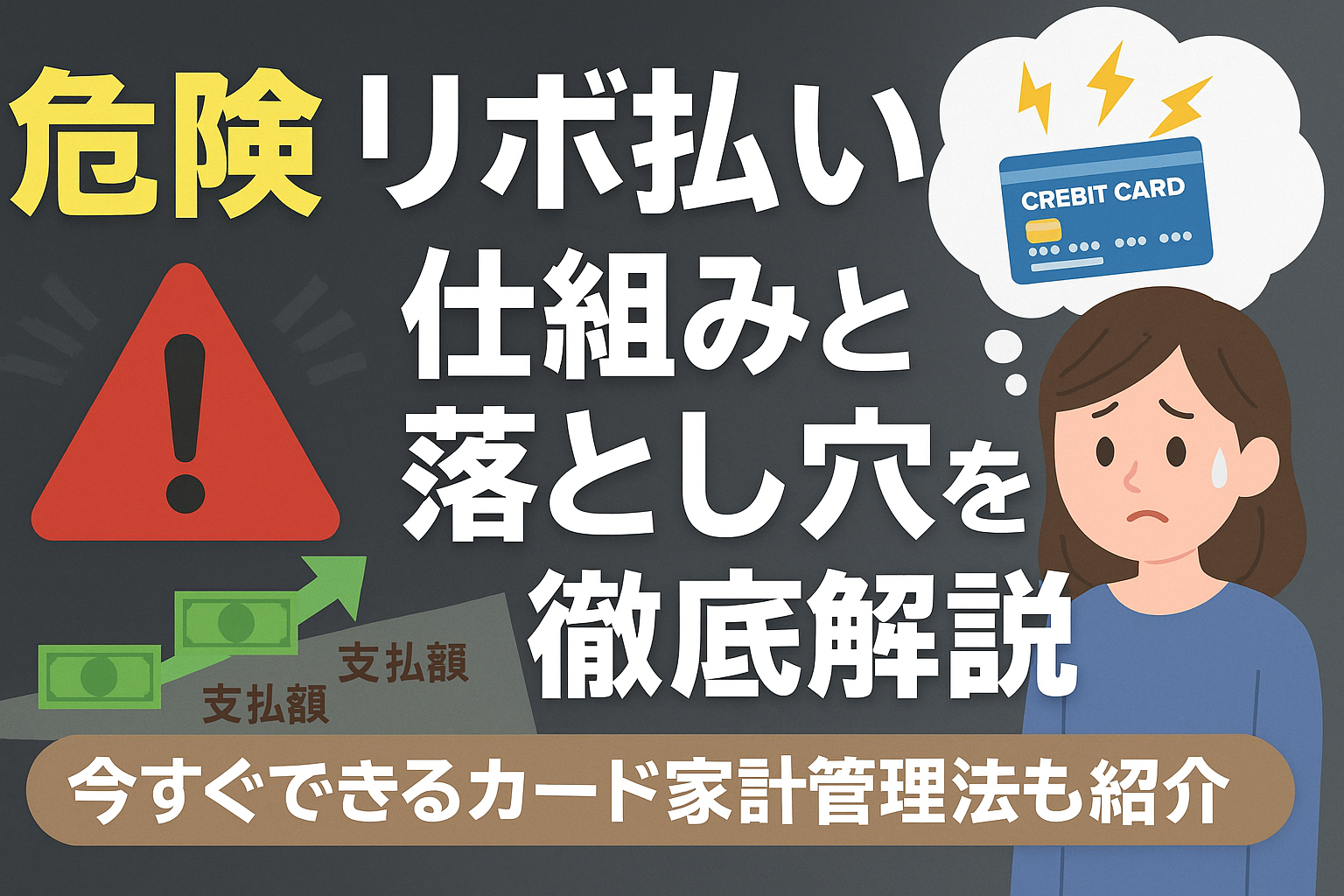
【危険】リボ払いの仕組みと落とし穴を徹底解説|今すぐできるカード家計管理法も紹介

2025年最新!クレジットカード&決済の未来:デジタル化、セキュリティ、お得な活用術を徹底解説

副業収入を賢く増やす!知って得する節税テクニックと会社バレ対策
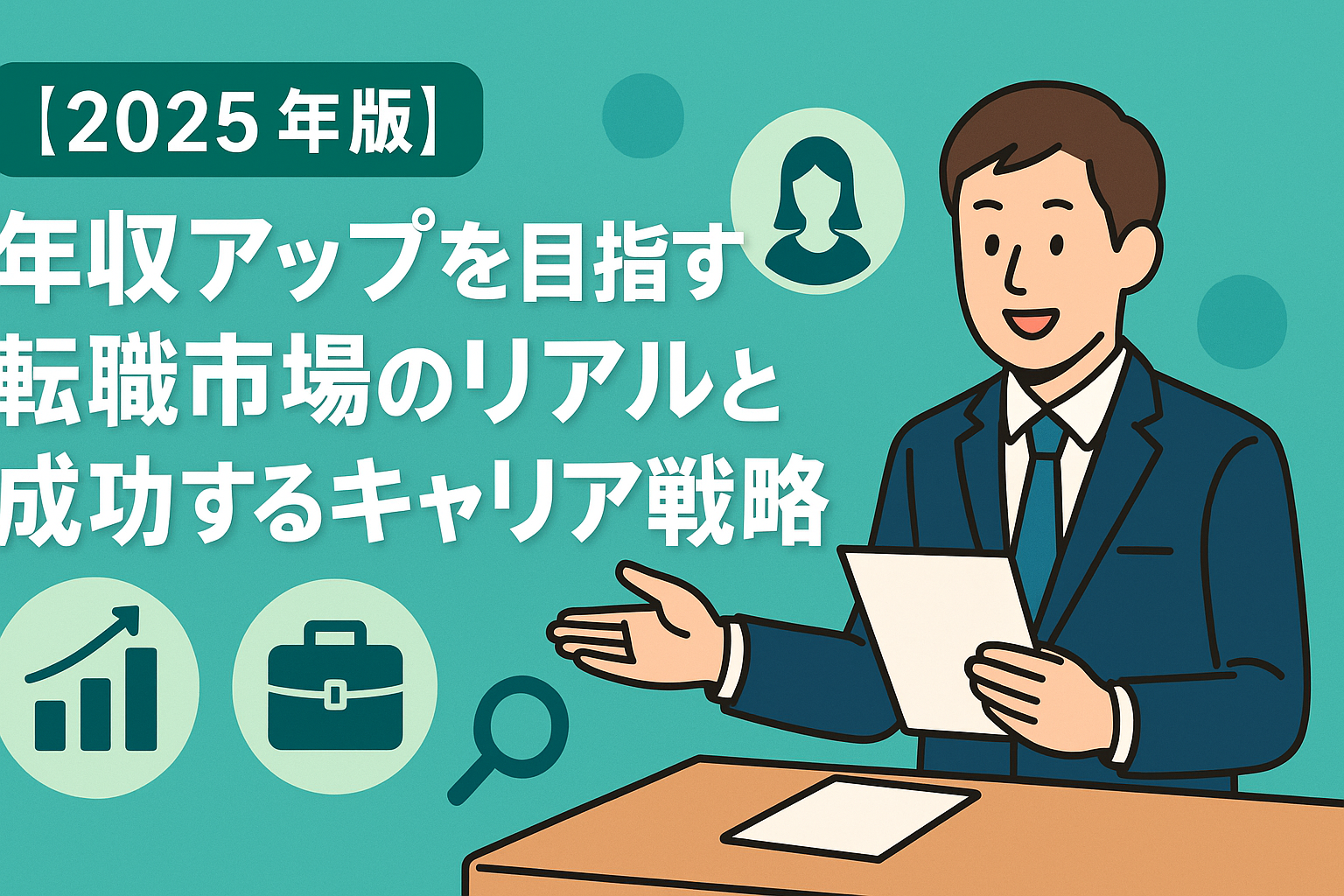
【2025年版】年収アップを目指す転職市場のリアルと成功するキャリア戦略
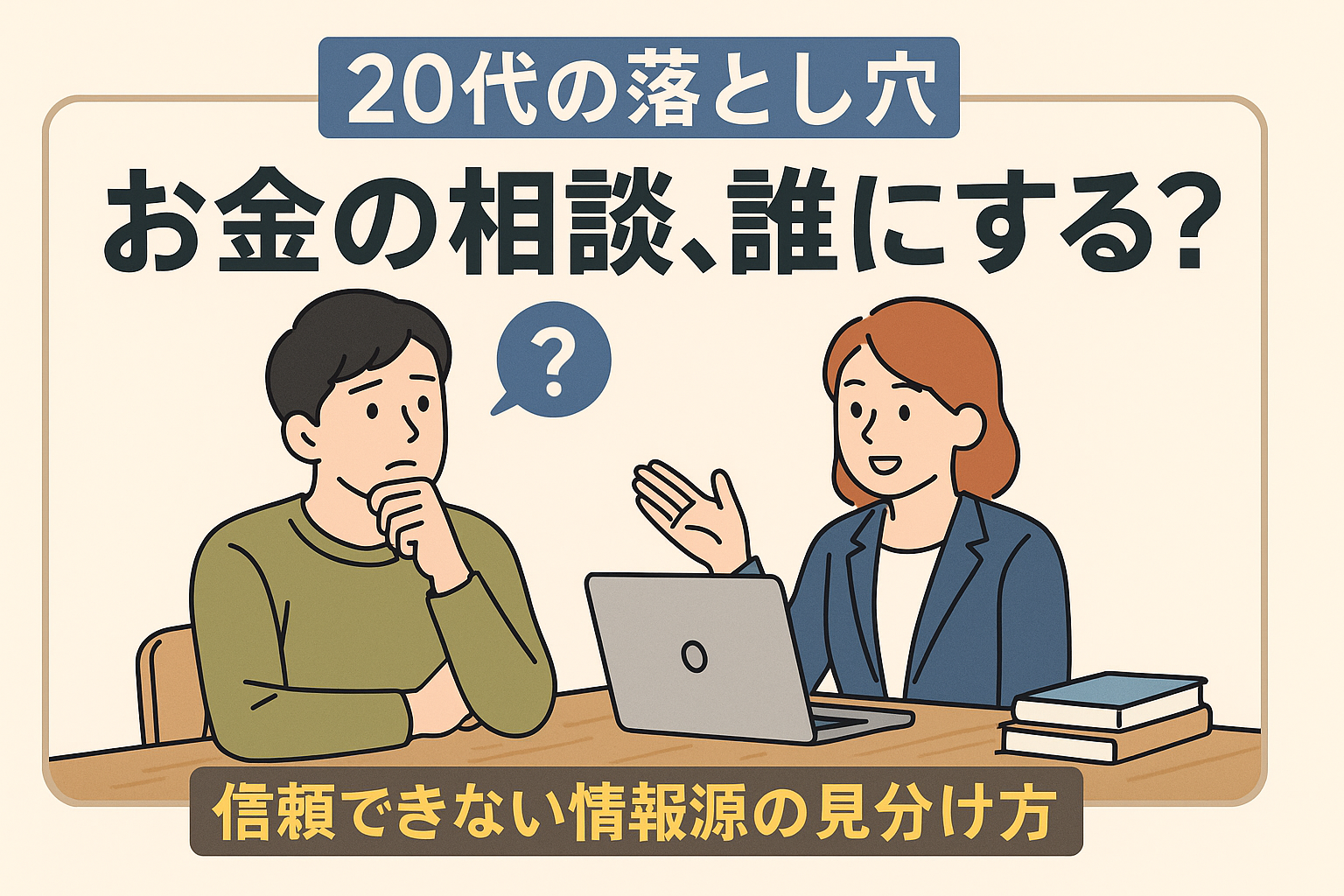
【20代の落とし穴】「お金の相談、誰にする?」信頼できない情報源の見分け方

【初心者向け】LINEスタンプの作り方完全ガイド!デザインのコツから収益化まで徹底解説

【祝・アドセンス審査通過】収益化までの道のり完全版!審査のコツと稼ぐための戦略
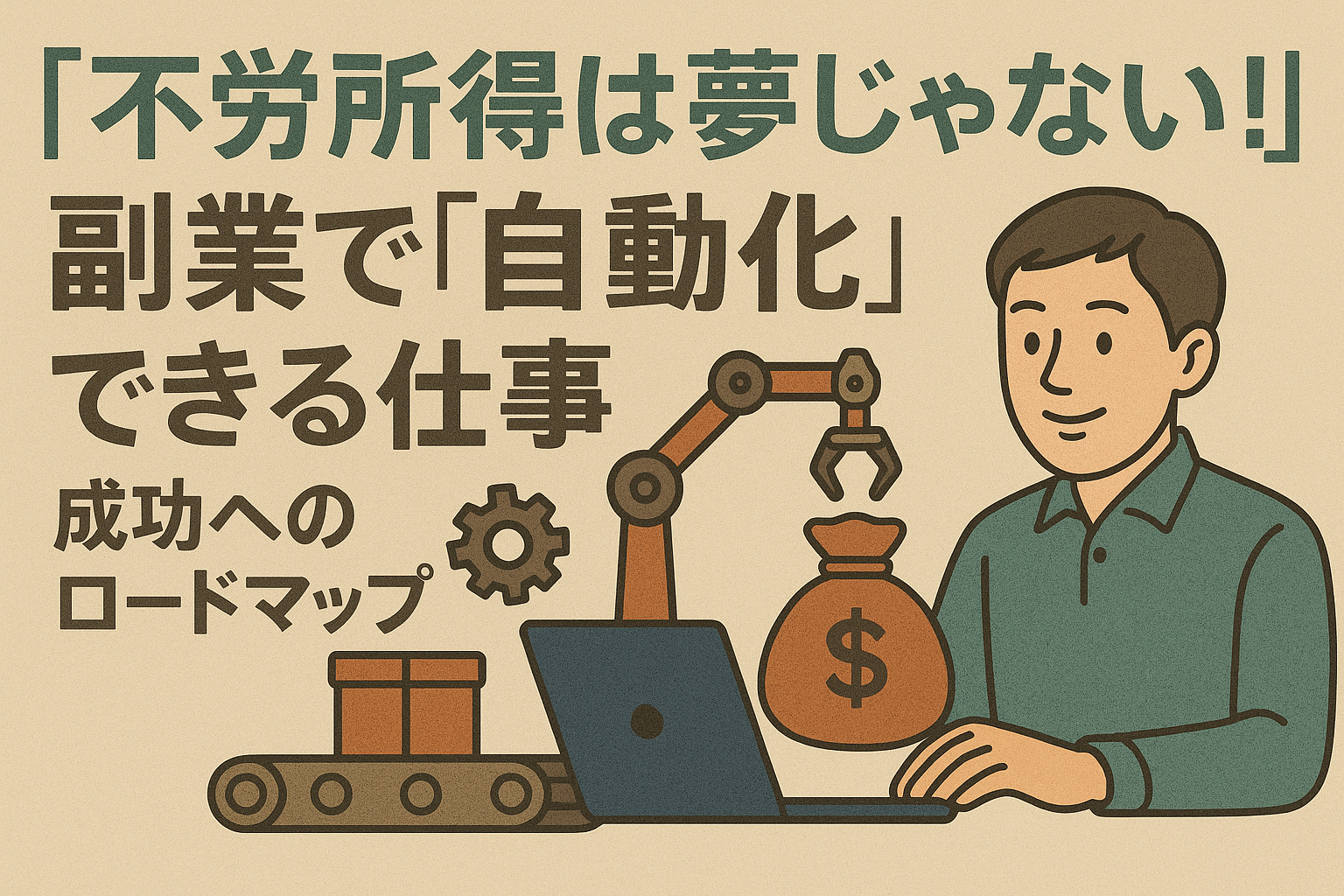
【不労所得は夢じゃない!】副業で「自動化」できる仕事と成功へのロードマップ
人気記事
Popular Post
Profile
はじめまして!神奈川県横浜市出身のかいちょうです。
AIと資産運用は、私たちの未来の働き方や暮らしを大きく変える、最も重要なテーマだと感じています。このブログでは、そうした最新の情報を皆さまに分かりやすく、そして楽しくお届けすべく、日々奮明しています。
専門的な話だけでなく、趣味の化粧品集めやPCの配線整理を通して、日々の生活の中にも「お金」や「効率」のヒントを見つけられるような記事も発信していきたいと思っています。
皆さまと一緒に、豊かな未来を築いていけることを楽しみにしています!どうぞよろしくお願いいたします。
プロフィールを読む